LCCは大手航空会社より危ないのでは?」と思ったことはありませんか?低価格を実現するLCC(ローコストキャリア)は、その便利さから利用者が年々増加していますが、一方で「安全性」に関して不安を感じる人も少なくありません。
しかし、実際にはLCCだからといって事故率が高いというわけではなく、安全性はさまざまな要因によって左右されます。このブログでは、「LCCに乗るのは危険?」という疑問に答えるため、航空事故に影響を与える本当の要因について解説していきます。LCCの運営体制や規制、運航環境を知ることで、その安全性を正しく理解していきましょう。
LCCの安全性、事故率が大手航空会社と変わらない理由
厳しい航空規制と監査はLCCにも課される
「LCCは安いから安全性が心配」という声をよく耳にしますが、実はそれは誤解です。航空業界は世界中で非常に厳しい規制のもと運営されており、この規制はLCC(ローコストキャリア)も大手航空会社も同様に課されています。「LCCだから危ない」という根拠はなく、むしろ低コストであっても高い安全基準を守っているのが現実です。その仕組みや背景を詳しく見ていきましょう。
世界中の航空会社は、それぞれの国の航空当局の監督を受けています。例えば、日本の国土交通省、アメリカのFAA(連邦航空局)、ヨーロッパのEASA(欧州航空安全機関)などの機関が代表的です。これらの機関は、航空機の運航や整備、乗員の訓練など、航空安全に関するあらゆる側面を監視しています。すべての航空会社は、この厳しい規制をクリアしなければ運航が許可されません。これはLCCも例外ではありません。
特に、LCCはそのビジネスモデルから効率性を重視しているため、一部の人々には「安全性が犠牲になっているのでは?」と思われがちです。しかし、実際にはLCCは最新の航空機を使用することが多く、整備の効率化を図るために同一機種を導入するケースが一般的です。この統一された機材は、整備や訓練のプロセスを簡略化し、結果として安全性の向上につながっています。新しい機材はトラブルの発生リスクが低く、運航スケジュールの信頼性も向上します。
また、航空会社は定期的な監査を受けることが義務付けられており、これもLCCと大手の違いはありません。監査では、航空機の整備記録、運航手順、パイロットや整備士の資格などが詳細にチェックされます。基準を満たしていない場合、運航停止や営業許可の取り消しといった厳しいペナルティが課されるため、航空会社側には安全性を維持する強い動機があります。このように、規制と監査がある限り、安全性を軽視する余地はありません。
「LCCだから危ない」というイメージの根本的な理由は、価格が安いことにあるかもしれません。しかし、LCCの低価格は安全性を削ることで実現しているわけではなく、効率化されたビジネスモデルや不要なサービスをカットすることで可能にしています。例えば、座席指定料や機内食をオプションとすることで、必要なサービスだけを選べる仕組みを提供しているのです。
LCCは新しい機材を使用していることが大半
「LCCは安いから古い機材を使っていて危険なんじゃない?」と考える人もいるかもしれません。しかし、実際にはその逆で、LCCは新しい機材を導入しているケースが多いのです。なぜなら、新しい機材は運営コストを削減できるだけでなく、安全性の向上にもつながるからです。この点について詳しく解説していきます。
LCCは低価格を実現するために効率的な運営を追求しています。その一環として、燃費が良く、メンテナンスコストが低い最新型の航空機を採用する傾向があります。例えば、ボーイング737やエアバスA320の最新モデルは、LCCで多く採用されています。これらの機体は、新しいエンジン技術や軽量化された機体構造により、燃料消費を大幅に削減できるのが特徴です。燃費が良いということは、コスト削減だけでなく環境負荷の軽減にも寄与します。そして何よりも、最新技術が搭載されているため、安全性が非常に高いのです。
新しい航空機には、パイロットの負担を軽減するための高度な自動操縦システムや、事故リスクを最小限に抑えるための最新の安全機能が装備されています。また、故障の兆候を事前に検知するモニタリングシステムが備わっているため、予防保全の観点からも非常に優れています。このような技術は、事故の可能性を大幅に減らすことに貢献しています。
さらに、LCCが新しい機材を使用するもう一つの理由は、機材を統一することで運営の効率化を図れるからです。例えば、すべての航空機を同一機種にすることで、整備士やパイロットの訓練が簡略化され、コスト削減につながります。パイロットは機種ごとに訓練を受ける必要がありますが、統一された機材であれば異なる機体に対応するための追加訓練が不要になります。この効率化により、運航スケジュールの信頼性が高まり、さらに安全性が向上します。
一方で、大手航空会社は幅広い路線網や運航規模の関係から、古い機材を引き続き使用するケースもあります。これはコストの観点や長距離運航の特性によるものですが、LCCと比較すると新しい機材の割合が少ない傾向があります。ただし、これが安全性に直結するわけではなく、大手も厳格な整備基準に従って運航しています。しかし、最新技術を活用するという点では、LCCの方が優れている場合も少なくありません。
また、LCCが新しい機材を導入する背景には、メーカーからの大量発注によるコスト削減も挙げられます。LCCは新興企業であることが多く、事業開始時に新機材を一括購入することで割引を受けることが可能です。このような経済的なメリットが、新しい機材を採用する後押しとなっています。
実際、航空事故の統計を見ても、LCCが大手航空会社よりも危険というデータはありません。むしろ、LCCは最新の安全機能を搭載した航空機を使用し、効率的な運営をしているため、トラブルの発生率は低い水準に抑えられています。
実はコスト削減は安全に影響しない
LCC(ローコストキャリア)はその名の通り、低価格な航空券を提供することが最大の特徴です。しかし、「安いということは安全性が犠牲になっているのでは?」と不安に思う方もいるかもしれません。実はその心配はほとんど必要ありません。LCCがコストを削減するのは、主に快適性やサービスの部分であり、安全性には一切妥協していません。これがどのように実現されているのかを詳しくお話しします。
まず、LCCがコストを削減する部分を見てみましょう。LCCは一般的に、機内サービスを簡素化し、無料の食事や飲み物の提供を行わないことでコストを抑えています。また、座席間のスペースが狭く感じるのも、機体の収容能力を最大限に活用するためです。さらに、空港ラウンジなどの付帯サービスを提供せず、大規模なハブ空港ではなく地方空港を拠点とすることも、コスト削減に貢献しています。これらの工夫は、乗客が必要としない部分を切り捨てることで実現されており、航空券の価格に直接反映されています。
一方で、整備や安全に関するコストは絶対に削減されません。航空業界では、安全性を軽視することが大きなリスクを伴うだけでなく、運営停止や罰則を受ける可能性があるため、どの航空会社もこの部分には厳密な基準を適用しています。LCCも例外ではなく、機体の整備や乗員の訓練には大手航空会社と同じく多大な投資を行っています。これは、航空当局が求める厳しい規制をクリアするために必要不可欠なことだからです。
例えば、LCCが使用する機材の多くは比較的新しいものであり、最新の安全機能を備えています。新しい航空機は、メンテナンスの頻度が少なくて済むだけでなく、故障のリスクも低くなります。また、LCCは機材を統一する傾向があり、整備士やパイロットの訓練が効率的に行える点でも安全性が向上します。このように、LCCが採用する運営モデルはコスト削減だけでなく、安全性の確保にも貢献しているのです。
また、整備や運航手順に関する監査も定期的に行われています。航空当局による厳格なチェックをクリアしなければ、どの航空会社も運航を続けることはできません。LCCであろうと大手航空会社であろうと、この基準は共通です。そのため、LCCがコスト削減を行っているからといって、整備や安全対策が疎かになることはあり得ません。
もう一つ、LCCが安全性を確保している理由として、効率性が挙げられます。例えば、LCCの多くは直行便を運航することで、飛行機の離着陸回数を減らし、トラブルのリスクを最小限に抑えています。さらに、短時間でのターンアラウンド(飛行機が到着してから次のフライトに出発するまでの時間)を実現するために、整備や乗員の動きを合理化しており、これも安全性を高める要因となっています。
一部の人々は「LCCは安全性にお金をかけていない」と誤解することがありますが、それはLCCが「無駄な部分」を削減しているだけに過ぎません。安全に関わる部分はむしろ厳しく管理されており、トラブルが発生した場合には速やかに対処できる体制が整っています。このように、LCCの運営はコスト削減と安全性の両立を目指しているのです。
パイロットや整備士の訓練は大手と同じ基準
LCC(ローコストキャリア)に乗る際、「大手の航空会社と比べて安全性に問題があるのでは?」と不安を感じたことはありませんか?その中でも特に気になるのが、パイロットや整備士の訓練の質かもしれません。しかし、実際にはLCCのパイロットや整備士は、大手航空会社と同じ基準で訓練を受けています。この事実を知れば、LCCに対する安全性の不安が解消されるはずです。
まず、パイロットについてですが、航空業界には世界共通の厳格な基準があります。パイロットになるためには、国際的に認められたライセンスを取得し、機材ごとの資格を満たさなければなりません。この基準はLCCであっても大手航空会社であっても変わることはなく、むしろ厳密に運用されています。例えば、パイロットが新しい機種に乗務する場合、その機材特有のシミュレーター訓練や実地試験を受ける必要があります。これらはすべて、大手航空会社のパイロットと同じプロセスで行われます。
LCCの多くは、コスト削減を目的として特定の機材に統一していることが多いのですが、この点がパイロットの訓練にもプラスに働いています。同じ機材を運用することで、パイロットが異なる機材に対応するための追加訓練が不要となり、その分、特定の機材に特化した深い知識とスキルを身につけることができます。例えば、エアバスA320やボーイング737といった機材に特化したLCCでは、パイロットはこれらの機材の性能や特性を熟知しており、トラブルが発生しても迅速かつ適切に対処できるように訓練されています。
整備士についても同様です。航空機の整備士は、国際的な規制や各国の航空当局が定める基準を満たさなければなりません。整備士が担当する作業には、細かいルールがあり、すべて厳密に記録され、監査されます。LCCの整備士は、大手航空会社の整備士と同じ基準で資格を取得し、訓練を受けています。また、LCCの運航においても、航空機が地上にいる間の短い時間で整備を行う必要があるため、効率性が求められます。この効率性を支えるのが、整備士の高度な技術と経験なのです。
また、航空会社全体が航空当局の監査を受けることは言うまでもありません。日本では国土交通省、アメリカではFAA、ヨーロッパではEASAといった機関がそれぞれの国の航空会社を監視しています。これらの監査では、訓練の質や整備の記録が厳しくチェックされ、基準を満たしていない場合は運航停止や改善命令が下されます。LCCも大手航空会社も、同じ基準で評価されるため、LCCだからといって基準が下がることは決してありません。
さらに、LCCのパイロットや整備士の訓練には、最新技術が活用されています。例えば、最新型のシミュレーターを使った訓練は、現実の飛行環境を忠実に再現し、あらゆるトラブルを想定して対応力を養うことができます。これにより、緊急時にも冷静に対処できるスキルが身につくのです。
一部の人々が「LCCは安全性が低い」と考えるのは、低価格ゆえに訓練の質を疑うからかもしれません。しかし、パイロットや整備士に関する訓練基準が共通である以上、このような懸念は杞憂と言えます。むしろ、LCCは運営の効率化によって、コストを削減しながらも安全性を維持することに成功しているのです。
飛行機事故が起こる主な原因
ヒューマンエラー:航空事故の最大の要因
飛行機事故の原因として最も多いのがヒューマンエラーです。統計によると、航空事故の50~80%はヒューマンエラーに関連していると言われています。これは、航空業界全体が最も重点的に取り組むべき課題でもあります。ヒューマンエラーには、パイロット、管制官、整備士といった航空業務に携わる人々によるミスが含まれます。以下に、それぞれの事例と影響について詳しく解説します。
パイロットのミス
パイロットによるミスは、ヒューマンエラーの中で最も直接的に事故に結びつくリスクです。操縦ミス、判断ミス、操作ミスといったエラーがこれに該当します。例えば、天候が悪化した際の着陸時に判断を誤り、滑走路をオーバーランしてしまうケースや、計器を読み違えて機体の高度を誤ることで山岳地帯に衝突するケースが挙げられます。こうしたミスを防ぐため、航空会社ではパイロットに対して定期的なシミュレーター訓練を実施し、あらゆる緊急事態に対応できるスキルを習得させています。
また、LCCのパイロットも大手航空会社のパイロットと同じ規制と訓練を受けており、LCCだからといって訓練の質が劣るわけではありません。むしろ、効率的な運営を行うLCCでは、特定の機材に特化した訓練が行われることが多く、特定機種への熟練度が高いというメリットもあります。
管制官のミス
航空機の離着陸や空中での位置管理を担う管制官のミスも、ヒューマンエラーの一つです。過密な空港では、管制官が多数の航空機を同時に管理する必要があり、一瞬の判断ミスが衝突事故など重大な事態を引き起こす可能性があります。例えば、滑走路上での誤った指示や、着陸許可を与えるタイミングのミスが挙げられます。
このリスクを軽減するために、多くの空港では最新の航空管制システムが導入されています。AIを活用した予測システムや、航空機同士の位置関係をリアルタイムで把握する技術が進化しており、人間のミスを補完する仕組みが整備されています。
整備士のミス
整備士によるミスもヒューマンエラーに含まれます。航空機の整備は極めて重要であり、一つのミスが重大な事故を引き起こす可能性があります。例えば、重要な部品の点検漏れや、エンジン部品の取り付けが不十分だった場合、飛行中にトラブルが発生するリスクがあります。
LCCでは、整備作業の効率化を図るために機材を統一するケースが多く、これが整備の精度を高める一因となっています。同じ機材を運用することで、整備士が特定の機材に熟知しやすくなるため、ミスの発生率を抑えることができます。また、すべての航空会社で、整備作業は二重チェックが義務付けられており、安全性を徹底的に追求しています。
機械的故障:航空機のメカニカルリスク
飛行機事故の原因の一つに挙げられるのが機械的故障です。近年ではボーイングの一部機体に関する問題が報告され、大きな注目を集めました。とはいえ、飛行機の設計や整備に関しては、各航空会社が厳密な基準を守っているため、機械的故障が直接的に事故につながるケースは稀です。それでも、技術的な不具合が発生した場合の影響が大きいことから、機械的故障は航空業界において継続的に監視される重要な課題です。
ボーイング737 MAXの事例は、機械的故障と設計上の問題が複合的に関与したケースとして知られています。このモデルでは、MCAS(自動操縦補助システム)の設計上の不備が原因で、複数の事故が発生しました。これを受けて、ボーイングは同機種の全世界的な運航停止措置を余儀なくされ、設計の修正と再評価が行われました。この出来事は、機械的故障だけでなく、設計上のミスが事故に結びつく可能性を浮き彫りにしました。
また、エンジンや油圧システムの故障も、機械的な問題として発生することがあります。しかし、現代の航空機は冗長性が高く設計されており、たとえ一つのシステムが故障しても、他のシステムがバックアップとして機能する仕組みになっています。このため、機械的故障が即座に重大事故につながることは少なく、乗客の安全はしっかりと守られています。
LCCは比較的新しい機体を運用する傾向があるため、機械的故障のリスクをさらに抑えることができています。最新型の航空機は、トラブルを未然に防ぐためのモニタリングシステムを搭載しており、整備士が早期に問題を発見できるよう設計されています。これにより、事故リスクがさらに低減されています。
機械的故障のリスクを完全になくすことは不可能ですが、航空業界全体での安全対策が進化する中で、その影響を最小限に抑える取り組みが続けられています。特にLCCも大手航空会社と同じ基準で機材を整備しているため、安全性について特別に不安を抱く必要はありません。
航空機の設計上のミス:過去から学ぶ教訓
航空機の設計上のミスは、事故の原因となることがあります。特に、過去に報告されたボーイング737 MAXの事例は、その一例として広く知られています。このモデルでは、自動操縦補助システム(MCAS)が設計上の欠陥を抱えており、それが重大事故を引き起こしました。これを受け、航空業界全体で設計段階の検証プロセスが見直されるきっかけとなりました。
航空機の設計上のミスは、製造段階でのテスト不足や運用環境の想定ミスによって発生することがあります。しかし、こうしたミスは非常に稀であり、事故が発生した場合でも原因が徹底的に調査され、再発防止のための改良が行われます。
近年では、航空機の設計にコンピューターシミュレーションやAIが活用されており、設計上のミスを未然に防ぐ取り組みが進んでいます。例えば、飛行中に受ける空気抵抗やストレスを詳細に解析し、安全性を最大限に高めるためのシステムが導入されています。
LCCが運用する航空機は、新しい設計が取り入れられた最新モデルであることが多いため、設計上のミスによるリスクはさらに低減されています。また、設計ミスが発覚した場合は、迅速に改修が行われ、航空機全体の安全性が向上しています。
航空機の設計上のミスは完全になくすことはできませんが、現代の航空業界は過去の教訓から学び、安全対策を進化させています。これにより、飛行機が最も安全な移動手段の一つであるという評価は今後も揺るがないでしょう。
サイバー攻撃:航空業界の新たなリスク
現代の航空機は高度にコンピュータ化されており、サイバー攻撃が新たなリスクとして注目されています。航空機はフライトプランや通信システムなど、多くの部分でデジタル技術に依存しており、これらが悪意ある攻撃の対象となる可能性があります。サイバー攻撃は発生しても公表されないケースが多いため、その全貌は明らかではありませんが、航空業界全体での対策が進められています。
サイバー攻撃には、航空機のシステムを直接妨害するものや、空港の運行管理システムを混乱させるものがあります。例えば、フライトプランが改ざんされることで航空機が誤ったルートを飛行してしまうリスクや、空港の通信システムが停止することで運航が遅延するリスクが挙げられます。
このようなリスクに対応するため、航空会社や空港ではサイバーセキュリティの強化が進められています。AIを活用した監視システムや、政府機関との連携によるリアルタイムの脅威分析がその一例です。LCCも大手航空会社と同じ基準でセキュリティ対策を講じており、特別にリスクが高いわけではありません。
バードストライク:自然との戦い
バードストライクとは、鳥が航空機に衝突する現象を指します。特に離着陸時に発生しやすく、鳥がエンジンに吸い込まれたり、機体に衝突することで損傷を引き起こすことがあります。バードストライクは航空業界において頻度は高いものの、重大な事故につながるケースは少なくなっています。
バードストライクのリスクを軽減するために、多くの空港では以下のような対策が取られています。
- 音響装置やライトを使用して鳥を追い払う
- 鳥類の飛来を監視するレーダーシステムを導入
- 空港周辺の鳥の生息地を管理し、生息数を減少させる
また、現代の航空機はバードストライクの衝撃を最小限に抑えるよう設計されています。エンジンの内部は鳥を巻き込んだ場合でも機能が維持されるようテストされており、機体そのものも衝突に耐えうる強度を持っています。
「LCC」or「大手」より、事故率に大きな影響を与える2つの要因
LCC(ローコストキャリア)を利用する際に、「LCCは大手航空会社より事故率が高いのでは?」と心配になる方もいるかもしれません。しかし、実際の事故率に影響を与える要因を見ていくと、LCCであるか大手であるかは、直接的な要因ではないことがわかります。それよりも重要なのは、地域ごとの安全規制の厳しさや、運航する空港や環境に関わる条件です。この2つのポイントを詳しく掘り下げてみましょう。
地域の安全規制の厳しさ
航空事故の発生率に大きく影響を与える要因の一つは、その地域の航空規制の厳しさです。先進国では航空規制が非常に厳しく設定されており、すべての航空会社が厳密に監視されています。例えば、日本の国土交通省、アメリカのFAA(連邦航空局)、ヨーロッパのEASA(欧州航空安全機関)といった機関が、航空会社や機体の安全性を厳しくチェックしています。このような地域では、LCCであっても大手であっても、安全性の基準は同じです。
一方で、規制が緩い発展途上国や、新興市場の地域では事情が異なることがあります。航空規制の基準が低かったり、監査が徹底されていなかったりする場合、航空会社全体の安全性が低下するリスクがあります。このような地域では、LCCだけでなく大手航空会社であっても、安全性に懸念が生じる可能性があります。つまり、事故率を語る上で重要なのは、航空会社がLCCか大手かではなく、その地域の航空当局がどれだけ厳密に安全基準を適用しているかという点なのです。
例えば、国際的な航空安全ランキングでも、規制が厳しい国々の航空会社は事故率が非常に低い水準にありますが、規制が緩い国の航空会社は全体的に事故率が高い傾向があります。この点を理解すれば、航空会社を選ぶ際に「LCCだから危険」と判断するのは早計であり、むしろどの国で運営されているかに注目すべきであると言えるでしょう。
運航する地域や空港の環境
航空事故率に影響を与えるもう一つの要因は、運航する地域や空港の環境です。過密空港や山岳地帯、悪天候が多い地域での運航は、リスクが高くなる傾向があります。例えば、世界的に見て事故が多い地域では、空港の設備や運航管理システムが整備されていない場合があります。これにより、着陸時のトラブルや空中での衝突リスクが増えることがあります。
また、山岳地帯や海沿いの空港では、風向きや気圧の変化が大きいため、パイロットには高度な操縦技術が求められます。このような厳しい環境下では、LCCか大手かに関わらず、運航リスクが高まります。ただし、多くの航空会社はリスクの高い空港やルートに適切な対策を講じており、パイロットの訓練を強化したり、天候データを詳細に分析したりすることで安全性を確保しています。
LCCは短距離路線を中心に運航することが多いため、過密な空港を利用するケースも多々あります。例えば、地方空港を拠点とするLCCでも、主要都市の大規模な空港へ乗り入れる際は、多くの航空機が同時に運航する中でスムーズに離着陸を行う必要があります。このような状況では、運航スケジュールの遅延やトラブルを防ぐために、整備の効率化やパイロットの迅速な判断が求められます。
さらに、悪天候の多い地域では、機体の性能やパイロットの経験が大きな意味を持ちます。LCCの多くが使用している最新の航空機は、悪天候に対応する高度なシステムを搭載しているため、この点では安心して利用できると言えます。一方で、大手航空会社が長距離路線で利用する古い機材では、このような最新技術が導入されていない場合もあるため、一概にLCCが危険とは言えないのです。
結局のところ、航空事故のリスクは「LCC」か「大手」かではなく、運航する地域の規制や環境、そしてそれに対する航空会社の対策次第です。価格の安さで判断するのではなく、航空会社がどのような地域や空港を利用し、どれだけ安全対策を講じているかに目を向けることが、安心してフライトを楽しむためのポイントです。LCCを利用する際も、このような背景を理解すれば、より安心して選べるようになるでしょう。
最新の事故率データ
具体的な事故率を知るためには、LCCと大手航空会社の事故数や飛行回数を基に計算された「百万飛行時間あたりの事故率」などが参考になります。
例として(ASNの2021年データ):
- 大手航空会社:1,000万飛行ごとに0.1件以下の致命的事故。
- LCC:大手とほぼ同等の水準(1,000万飛行ごとに約0.1~0.2件)。
まとめ:LCCはやばくないです
LCCの安全性に対する不安は、「安い=危険」というイメージからくる誤解であることが多いです。実際には、LCCも大手航空会社と同じ規制のもとで運営されており、機材の整備や乗員の訓練に妥協はありません。事故率に影響を与えるのは、LCCか大手かではなく、運航する地域の規制の厳しさや空港の環境といった外部要因が大きいのです。最新技術を導入し、効率的な運営を行うLCCは、むしろ現代の航空業界において安全性が高い選択肢であると言えます。次回、LCCを利用する際には、こうした背景を知って、安心して空の旅を楽しんでください。「安いけど危ない」はもはや過去の話。LCCは安全で快適な旅を提供する、現代の頼れる移動手段です。
【英語は、人生で3ヶ月だけ集中学習すれば誰でも話せるようになります】

「オンライン英会話を一年以上続けてるのに、全然話せるようにならない」「英会話教室にずっと通ってるけど、お金ばっかりかかって効果が感じられない」と感じていませんか?
だったら英語コーチングに切り替えましょう。
大人の日本人は、ただがむしゃらに英語を話す練習ばかりしていても、なかなか英語を話せるようになりません。そのやり方が通用するのは英語と母国語が似たドイツ人やイタリア人、フランス人などの欧米人だけです。
必死に冷や汗かきながら会話練習するのは、まるで「サッカーで試合に勝ちたいから、とにかく練習試合をしまくる」みたいなもの。そんなので勝てるわけがないですよね?同様に、
日本人に必要なのは、第二言語習得研究をベースとして科学的英語トレーニングです。専属英語コンサルタントによる英語習得までの戦略立案、綿密に計算された英語トレーニング、英語の専門家による直接指導です。そしてそれを実行するための行動管理です。
今人気の英語コーチングでは、多くの人が3ヶ月で驚くほど英語力を上げています。会話力で言えば「3ヶ月で会社での英語プレゼンが緊張せずにできるレベルに」、TOEICでいえば「2ヶ月で300点アップ」も現実的な範疇です。
私自身、有名な英語コーチングの「STRAIL」と「PROGRIT」を受講して今ではTOEIC985点。東南アジアやヨーロッパで自由気ままに暮らしています。
3ヶ月で人生が変わります。ぜひ英語コーチングを体感してみてください。↓↓
3ヶ月で話せるように!究極の英語サービス!
(※1分で無料体験申し込みOK)
②初心者OK、日本最高峰の英語パーソナル → ENGLISH COMPANY
③本田圭佑も受講!ビジネスエリートに人気 → PROGRIT
| 4位 | ||||
 |  |  | 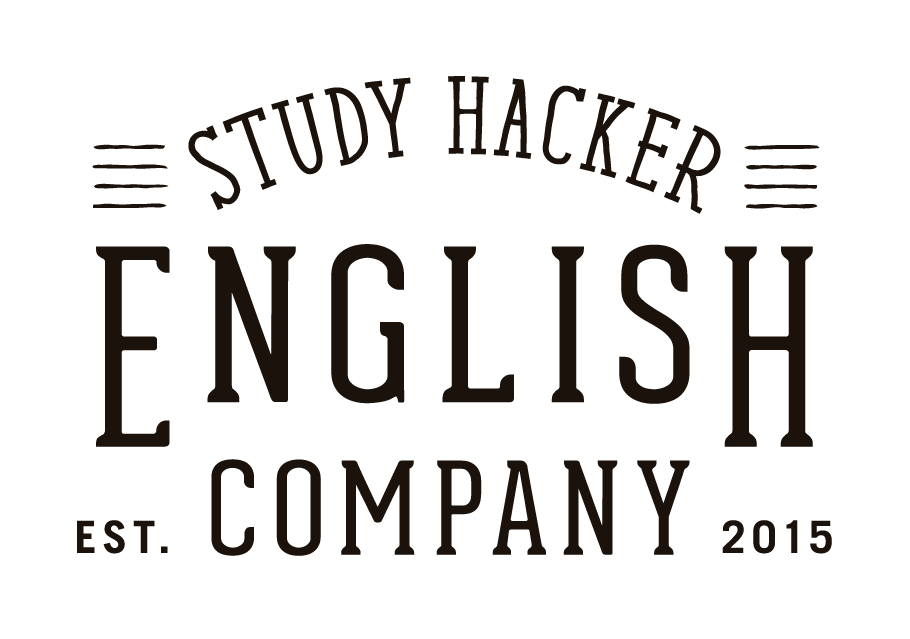 |
|
| 公式サイト | STRAIL | プログリット | トライズ | ENGLISH COMPANY |
| 期間 | 3ヶ月 | 3ヶ月〜 | 1年 | 3ヶ月〜 |
| コース | ビジネス英語 初級者 TOEIC(300点UP の実績多数) | ビジネス英語 TOEIC・TOEFL IELTS | 1年プログラム | パーソナルトレーニング セミパーソナル |
| オンライン受講 | ||||
| 日本人講師 レッスン | 週1回 | 週1回 | 週1回 | 週2回 |
| 英語コンサル | 週1回 | 週1回 | 週1回 | 週2回 |
| 講師 | 専門家レベル | |||
| 1日の学習時間 (学習効率) | 1.5時間 | 3時間 | 3時間 | 1.5時間 |
| アウトプット | 専属日本人講師 マンツーマン | オンライン英会話 | オンライン英会話 グループ | 専属日本人講師 マンツーマン |
| 教材 | 垂直統合型 学習デザイン | 他社教材組合せ | 他社教材組合せ | 垂直統合型 学習デザイン |
| 累計受講者数 | 28,000 | 18,000人 | 12,000人 | 28,000人 |
| 法人導入例 |    |   |  |    |
| 全国校舎数 | 計11校 | 11校 | 10校 | 計11校 |
| 基本料金 (1ヶ月) | 297,000円 (99,000円) | 544,500円 (181,500円) | 1,284,000円 (107,000円) | 561,000円 (187,000円) |
| 他コース | 延長プラン | 6ヶ月: 1,069,200円 | セミパーソナル: 231,000円〜 |
|
| 一般教育訓練 給付制度 | 受講料20%OFF | 受講料20%OFF | 受講料20%OFF | 受講料20%OFF |
| 30日間全額 返金保証 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 無料体験の感想 |  |  |  |  |
| 詳細記事 | レビュー | レビュー | レビュー | レビュー |
| 公式サイト | STRAIL | プログリット | トライズ | ENGLISH COMPANY |
